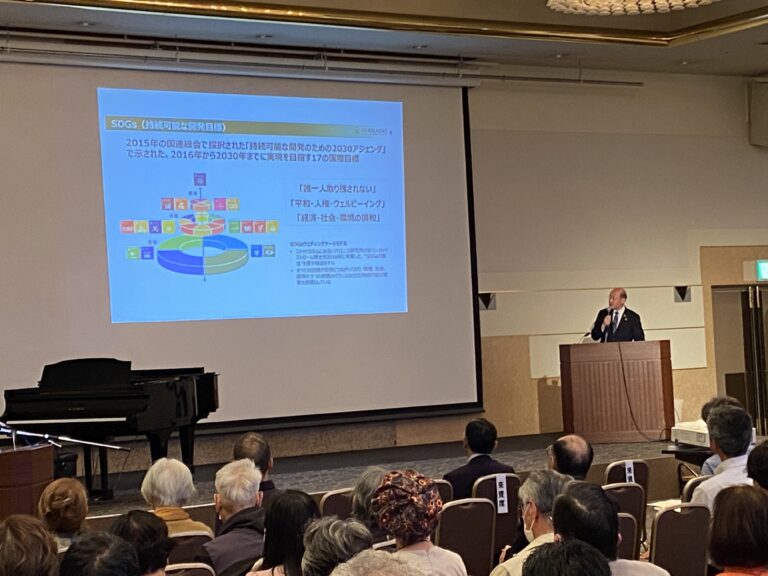6月15日、学校法人同志社及び同志社校友会北海道支部は2025年に創立150周年を迎えることを記念して「同志社創立150周年 記念講演会 in札幌」をホテルポールスター札幌で開催しました。
今回、両大学が150周年を迎えること(北海道大学:2026年。同志社:2025年)、クラーク氏の教えを受け同時期に創設された高等教育機関であることから、同志社が札幌で行う記念講演会を北海道大学が後援することとなりました。
1875年に同志社英学校を設立した新島襄は、札幌農学校(現北海道大学)の初代教頭となるウィリアム・スミス・クラーク氏とアメリカ・アマースト大学で師弟関係であり、クラーク氏が北海道赴任を決めたのは、新島襄の影響があったとされています。
1876年に札幌農学校を設立した開拓使次官の黒田清隆は、米国から招へいしたお雇い外国人元農務長官ホーレス・ケプロンの進言に基づき、米国州立マサチューセッツ農科大学から外国人教師を迎え、その一人が新島襄の師たるクラーク氏でした。
両大学の浅からぬ関係に基づき行われた記念講演会は、北海道大学混声合唱団と同志社グリークラブのジョイント・コンサートで始まりました。
岩見沢市出身の同志社OGの実家が寺院であり、同OGが同志社グリークラブの関係者であった縁で、両団体は以前よりコラボ経験があり、同志社創立150周年記念行事に声が掛かかりました。
コンサートでは、札幌農学校寮歌「都ぞ弥生」がフーガを交えて合唱された他、アメリカ南北戦争時の北軍行進曲「Tramp!Tramp!Tramp!」を原曲とする、北海道大学「永久の幸」、同志社大学「若草萌えて」が披露されるなど貴重な機会となりました。
その後、同志社総長・理事長八田英二氏の挨拶があり、両大学から1名ずつの講演者から講演がありました。
北海道大学からは横田理事・副学長が「北海道大学のサステイナビリティ追求の歴史と現在地」と題して講演を行いました。講演では、現在のサステイナビリティを追求する北海道大学のDNAが札幌農学校にあること、単なる農学教育だけではない、幅広い教養を教える全人教育があったこと、札幌農学校を大学に推し進める基礎は、クラークの教えを受けた1期生の佐藤昌介が米国留学で学んだモリル法に基づくことなどが説明され、その後、本学の現在の取り組みが説明されました。
2番目の講演は、同志社大学同志社社史資料センター社史資料調査員小枝弘和氏から「William Smith Clarkと新島襄-両者が紡いだ北海道と京都の縁-」と題して行われました。
クラーク氏と新島襄の師弟関係に端を発する『新島襄と札幌独立基督教会』及び『同志社大学設立運動と札幌独立基督教会』との関係が、調査した資料から導き出される史実として紹介されました。特に、後者の同志社大学設立運動においては、北海道毎日新聞社が半年余りの間に募金募集の社告(無償)を80回も掲載したこと、同社に札幌農学校6期生で札幌独立基督教会所属の者がいたこと等が紹介され、同志社と札幌農学校の知られざる関係が説明されました。
最後に、同志社校友会北海道支部の草野支部長から挨拶があり、後援した北海道大学に謝辞が述べられ、盛況のうちに閉会となりました。